慶應義塾大学名誉教授 教育学博士 安藤寿康氏
行動遺伝学研究の第一人者が語る知能・学力に関する遺伝。
① 遺伝の影響を受けるもの、受けないもの
遺伝の影響を受けないものはないですが、遺伝だけで決まるものはありません。
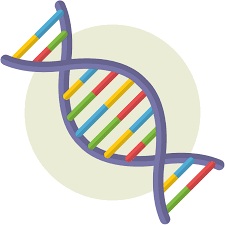
知能・学力に影響する遺伝
学力に関係する遺伝子は3900種類ほどあります。
知能の遺伝は行動遺伝学で最もよく研究されていて、1960年ぐらいから結果が出揃っています。
知能・学力は50~60%(約半分)遺伝の影響を受けます。
IQが遺伝の影響が一番強いと言えます。
なお、家庭環境も30%影響します。
IQと学校の成績は相関は高いです。
そもそも、IQは学校についていけるかどうかを調べる目的で、1905年にアルフレッド・ビネーによって作られたものです。
知能と学業の双生児相関関係数のグラフを見ると、
小学生
国語・社会・図工・体育に遺伝の影響が強く出ています。
中学生
国語・社会・美術・技術・英語に遺伝の影響が強く出ています。
理数系に遺伝の影響が強く出ないのは日本の特徴です。
おそらく、公文式や他の塾などで理数系の学力を上げているからと考えられます。
知能と学業への遺伝の影響の割合
児童期40%程度
青年期55%程度
成人初期65%程度
歳を重ねるごとに遺伝の影響が強く現れるようになります。
子供の頃は、親や周囲の大人の言うことに従って勉強しますが、年齢が上がると、自分の遺伝子に合った環境で独自に学んでいくようになるためです。
IQの高さは子供の頃から表に現れます。
たとえば、マシュマロ・テストの例があります。
1960年代にスタンフォード大学の心理学者、ウォルター・ミシェルによって行われた実験です。
4~6歳の子どもを個室に入れ、テーブルにマシュマロを1つ置き、研究者が部屋を出て15分待てばもう一つマシュマロをもらえると説明します。
我慢して2つマシュマロをもらった幼児の追跡調査では、のちの学業成績が良好で、社会的な地位や収入も良好であったという結果が示されました。
ポリジェニックスコア
学力に関する3900程度の遺伝子を解析し、遺伝子の塩基配列の違いを探し出し、塩基ごとの影響度を算出して合計したものがポリジェニックスコアといいます。
このスコアによって、有名大学進学までするのかしないのか、途中でドロップアウトするのかしないのかを予想できます。
ポリジェニックスコアは、体質や健康についても分かります。
そちらの分析は、数万円で商業化されています。
子どもが持っている好き嫌いは、遺伝の作用によるものなので、一生のものになっていく可能性が高いです。
子どもに遺伝した才能は、気付かなかったり、過小評価している場合が多いと思います。
今、子どもが好きなことは、将来の素質の種になっている可能性があるのです。
もちろん環境もとても大事です。
子どもは環境の中で生きていて、環境から能力という栄養を摂取してますから。
野球選手のイチローさんの言葉で、「1%の才能と99%の努力」というものがありますが、努力も遺伝によります。
努力をし続ける才能に関する遺伝子の影響です。
あることに対しては努力を続けられるが、その他のことについては全く努力できないというのも遺伝です。
どのような力も遺伝なのです。
と言っても、今の科学で説明できるのは全体の15%程度です。
学力のポリジェニックスコアが悪いからと言って、その通り将来が決まるというわけではありません。
② 家庭環境で親にできることはなにか?
・子どもに読み聞かせをする。
・読書をさせる。
以上は、子供の学力に良い影響を及ぼします。
・親が子どもに「勉強しなさい」と言わないこと。
・子どもをよく観察する。
・・・・・・・
「②家庭環境で親にできることはなにか?」以降については次回に書きます。





コメント