一時、行動経済学という分野が流行り、多くの本が出版されました。
心理学と経済学の両面から、人はどのような心理でどのように行動するのかということを解明する学問です。
経済学というとケインズ経済学とかマルクス経済学などが頭に浮かび、とっつきにくい感じがします。
ところが、行動経済学の場合は、「子供の成績を上げるためにはどうすればいいか?」などの身近な問題を扱うことができるので親しみやすいです。
しかも、テストでよい点を取った時には「褒めるだけ」「トロフィーを渡す」「お金を渡す」などの実験を行いその効果を調べていきます。
もしご興味があるのであれば、
「その問題、経済学で解決できます」
ウリ・ニーズィー/ジョン・A・リスト 著

をお勧めします。
めちゃくちゃ面白かったです。
「行動経済学が最高の学問である」
相良奈美香 著
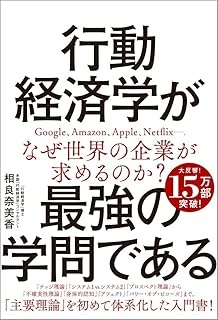
もお勧めです。
こちらも面白かったです。
さて、行動経済学の手法を教育に取り入れて、エビデンスの伴った教育論を展開しておられるのが、中室牧子教授の「学力の経済学」です。
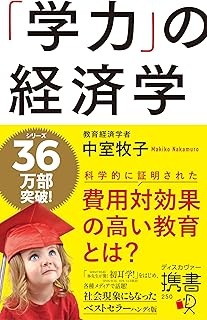
以前、こちらブログで少し書かせていただきました。
面白かったのは、教育論になると日本人全員が自分の教育論を語りだすと書かれている点です。
たしかに、「関税」問題について、「私の経験では、関税というのは・・・・」と語り出す人はあまりいないでしょう。
ところが、「教育」となると、皆「私の経験では、・・・・」と語り出すというのです。
その理由は、皆教育を受けてきたからと指摘されております。
ところが、それらはエビデンスのない主張であって、あくまでも個人の感想にすぎないと書かれています。
その通りだと思います。
大雑把ではありますが、「学力の経済学」の内容をご紹介したいと思います。
1.他人の成功体験はわが子にも活かせるのか?
答え:他人の子育て成功体験を真似しても、自分の子供もうまくいく保証はない。
家庭の環境、子供の性格、親の性格、子供の能力、親の能力、親子の関係などなど、子育てには要素が死ぬほどあります。
それらの要素がほぼ一致しているなら別ですが、そうでないならば、真似をしても同じ結果が出るとは限らないというのは当然のような気がします。
2.子どもをご褒美で釣ってはいけないのか?
答え:釣ってもいい。
ご褒美を与えることは、子供の「一生懸命勉強するのが楽しい」という気持ちを失わせるわけではない。
↑これもちゃんとエビデンスがあります。
すぐに得られるご褒美を設定すると、今勉強することの利益を理解し、満足を高める。
ご褒美の内容は「本を読む」「宿題をする」などのインプットに与えるべき。
「テストの得点」などのアウトプットに与えてはいけない。
3.子どもを褒めたほうがいいのか?
答え:いい!
褒めるときには、「宿題よくがんばったねー」などのように、具体的に達成した内容を挙げて褒めることが重要。
「頭いいねー」などのように、もともとの能力を褒めない方がいい。
達成できない場合に、自分は頭が悪いと思い込んでしまうから。
成績が悪かったり、目標を達成できなかった子の自尊心をむやみに高めることを言うのは逆効果。
※別の著書によると、アメリカの実験では、努力しないのに偉そうな子供が大量生産されたそうです(笑)
4.ゲームばかりしているので禁止するほうがいいのか?
答え:1日1時間までならゲームやって問題ない。
2時間以上だと学習時間などへの問題が生じてくる。
5.幼児の頃から教育にお金をかけるべき?
答え:人的資本への投資は、とにかく子供が小さいうちに行うべき。
一般により多くのお金が投資される高校や大学のころになると、人的資本投資の収益率は、就学前と比較すると、かなり低くなる。
幼児教育への財政支出は、社会全体でみても割の良い投資。
6.学校での勉強は本当にそんなに大切なのか?
答え:とても大切
学校は、学力に加えて、非認知能力を培う場でもある。
非認知能力は将来の年収、学歴や就業形態などの労働市場における成果に大きく影響する。
※非認知能力とは、意欲や協調性、自制心など、数値化できない人間的な能力
しつけは勤勉性という非認知能力を培う重要なプロセス。
部活や生徒会も非認知能力を鍛える手段となりうる。
かいつまんでご紹介いたしましたが、これらの内容のエビデンスを知りたい方は、「学力の経済学」をご購入ください。
古本ならば500円前後で売っています。
Amazon unlimitedをご利用の方は0円です。





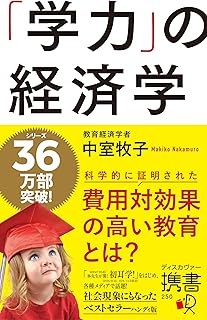
コメント